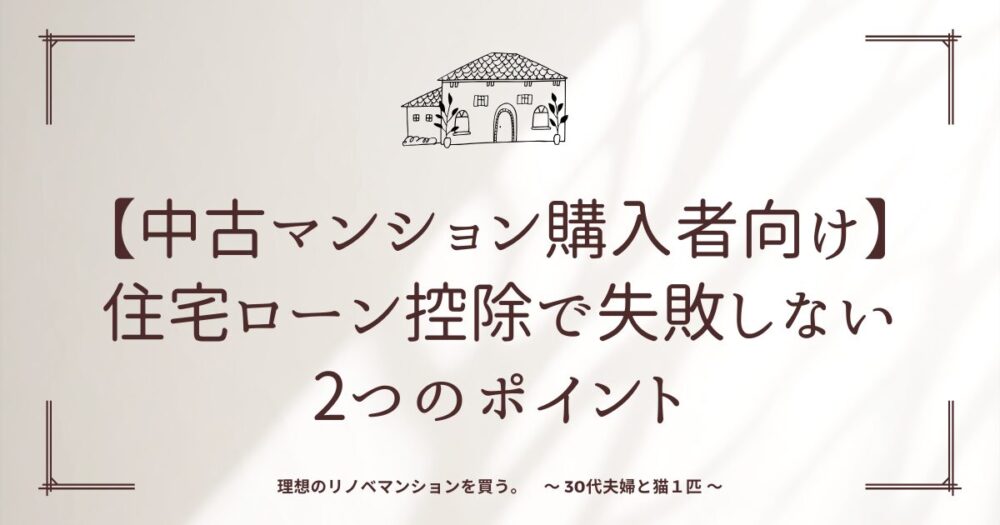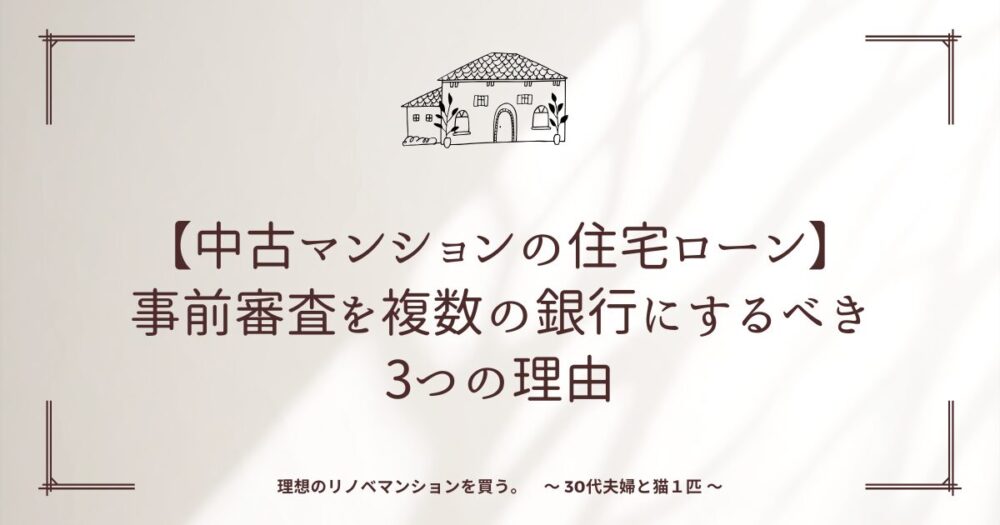【ポイントを解説】リノベーションマンションと住宅ローン
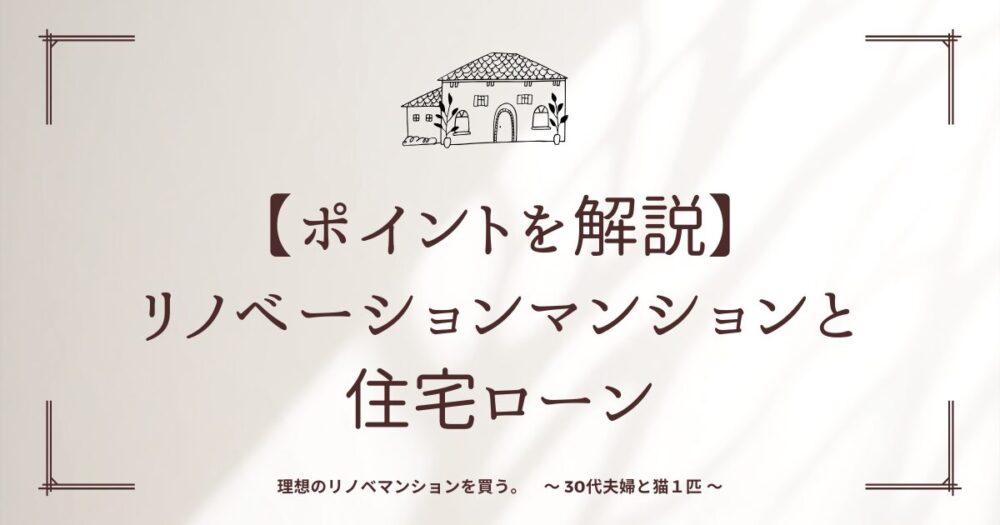
リノベーションマンションと住宅ローンについて

あなたは「リノベーションマンションを購入する際のローンの組み方」についてご存じですか?
私も購入を考えるまでは、新築と同様に住宅ローンを組むのだろうと漠然と思っていました。
しかし、実際には少し異なる点があるため、ここでは注意点について説明します。
ワンストップ型のリノベーション会社を利用すると、提携ローンが自動的に紹介されることが多く、そのため特に違和感なく進められることが一般的です。
しかし、その選択が金利に影響を与えることがあります。
今回は購入者の視点でのブログですので、ぜひ最後までご覧ください。
このブログを読むとわかること
- リフォームローンと一体型住宅ローンのメリット・デメリットがわかる
- リノベマンションでの住宅ローンならではの注意点がわかる
リノベーションに使えるローンの種類は?
中古マンションを購入して、リノベーション費用についてもローンを組む場合には、2種類の選択肢があります。
- リフォーム一体型住宅ローン(以下、一体型ローン)
- リフォームローン + 住宅ローン(以下、リフォームローン)
断然、①のリノベーション一体型住宅ローンがおすすめです。
②のリフォームローンもありますが、リノベーションマンションの購入には適していません。
リフォームローンは担保を取られないというメリットがありますが、借入金額が比較的少ないため、住宅購入には不向きです。
リフォーム一体型住宅ローンのメリット・デメリット

リノべ会社を利用するならば、一体型を選ばない理由がありません。
下記がメリット・デメリットになります。
メリット
- 低金利:一般的なリフォームローンと比べて金利が低く、通常1%程度で借りられます。
- 長期の返済期間:最長35年程度の返済期間が設定できるため、月々の返済負担を軽減できます。
- ローン管理の簡素化:住宅購入とリフォーム費用を一本化できるため、返済計画が立てやすく、管理が容易になります。
- 諸費用と手続きの削減:ローンを一本化することで、諸費用を抑えられ、事務手続きも1回で済むため、時間と労力を節約できます。
- 住宅ローン減税の適用:リノベーション一体型ローンの場合、住宅ローン減税が適用されるため、金銭的負担がさらに軽減されます。
デメリット
- 抵当権設定によるリスク:抵当権が設定されるため、返済不能時に家や土地が差し押さえられるリスクがあります。
- 複雑な審査:工事の見積書や計画書が必要となり、審査がより複雑になります。
- 取り扱い金融機関の制限:このタイプのローンを提供している金融機関が限られています。
- 融資審査の難易度:通常の住宅ローンと比べて、融資審査の難易度が相対的に高くなる傾向があります。
- 抵当権設定費用:抵当権の設定に伴う費用が発生し、ローン手続きの諸費用が増加する可能性があります。
リフォームローンのメリットとデメリット

中古マンションを購入したが、「キッチンだけは直したい」「洗面所は綺麗にしたい」などオプションのようにしたが、資金がない人のみが対象ですね。
下記が、メリットとデメリットになります。
メリット
- 担保不要:
無担保型のリフォームローンは、担保を提供する必要がないため、手続きが簡単で迅速です。また、抵当権設定費用も不要です。 - 審査が比較的容易:
住宅ローンに比べて審査基準が緩やかで、審査がスピーディーに行われるため、急な資金需要にも対応しやすいです。 - 少額から借り入れ可能:
融資下限額が低く、少額の借り入れができるため、小規模なリフォームにも適しています。
デメリット
- 借入限度額が低い:
無担保型のリフォームローンは借入限度額が低く、通常50万円から500万円程度です。大規模なリフォームには不向きです。 - 金利が高い:
無担保型のリフォームローンは金利が高めで、通常2%から5%程度です。これにより、返済負担が大きくなる可能性があります。 - 返済期間が短い:
返済期間が短いため、毎月の返済額が高くなる傾向があります
中古を買ってリノベーションする場合の注意点

新耐震基準が好ましい
多くの金融機関は、中古住宅への住宅ローン貸付の条件として、新耐震基準を満たしていることを求めています。
リノベーションマンションと言うと、築40〜50年の物件をリノベーションするイメージが多いかもしれませんが、新耐震基準は確認申請が1981年6月以降の建物です。
築40年を超えるマンションの多くは旧耐震基準に基づいています。
そのため、マンションを購入できないわけではありませんが、金融機関の選択肢が限られるため、金利が予定よりも高くなる可能性があります。
営業担当者は「旧耐震基準でも問題なくローンは組めますよ」と言うことが多いですが、金利が高くなるという点には触れないことが多いです。

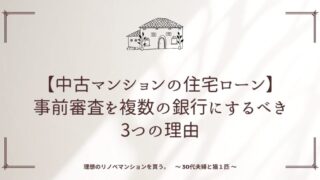
複雑な審査:工事の見積書や計画書が必要となり、審査がより複雑
通常の住宅ローンであれば、あまり細かいことを考えずに手続きを進められます。
仮審査から本審査まで、スムーズに流れていくことが多いです。
しかし、リノベーションマンションの場合は、中古マンションの購入に加えてリノベーション工事の手続きが入るため、少し複雑になります。
仮審査までは特に問題なく進みますが、本審査では、借入額が確定しないと話が進みません。
さらに、工事の見積もりや計画書を提出する必要が出てきます。
ここで重要なのは、リノベーションプランをある程度固めておくことです。
私の場合、必要な手続きが3週間ほどしかないと言われました。
この短い期間の中で、やりたいことが予算内で収まるか、しっかり確認する必要がありました。
予算が少なすぎると希望のリノベーションができませんし、多く借りようとすると審査が通らないという悩ましい状況になりますね。
リノベーションマンションでも住宅ローン控除が対象になる
リノベーションマンションも住宅ローン控除が対象になります。
ただし、諸条件を満たさないと適用されませんので、注意が必要です。
下記に住宅ローン控除について、まとめたブログになりますので、ご覧ください。
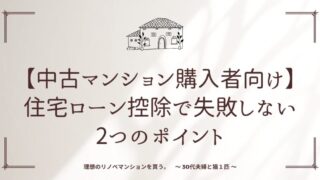
【まとめ】リノベーションマンションと住宅ローン
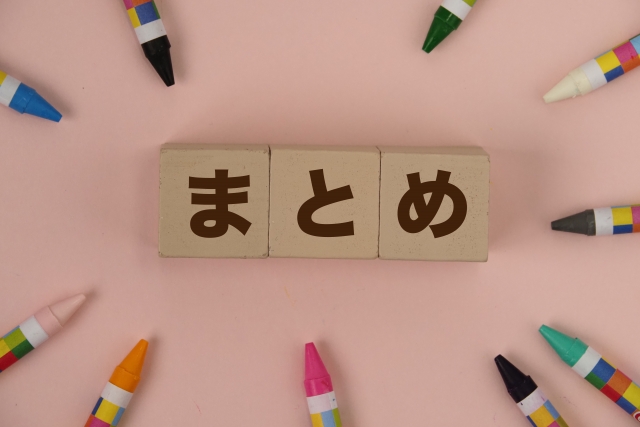
リノベーションマンションを購入する際には、一体型ローンを選ぶべきです。
プランをある程度固めておくことが重要で、事前にリノベーション会社に自分たちの要望を伝えておくことで、金額のブレややりたいことが実現できないリスクを防ぐことができます。
リノベーションを選ぶ理由は、注文住宅のように自分たちの希望に合ったマンションを購入したいからだと思います。
それが実現できなければ非常に残念ですので、しっかりと準備をして、理想の住まいを実現するために頑張りましょう。
「あまり考えたくないよ」って思う人
信頼できる営業担当がいる場合や、多少の金銭的余裕がある方は、リノベーション会社にお任せするのも良い選択です。
特に、迅速に対応する必要がある場合、リノベーション会社のノウハウが大いに役立ちます。
彼らは経験豊富で、スムーズにプロセスを進めることができます。
「少しでも安く」という人
時間がない場合でも、選択肢を狭めないことが重要です。
住宅ローンはわずかな違いで数百万円の差が生じることがあります。
そのため、スピード感が大事です。早い段階で事前審査を通しておくと良いでしょう。
私は最初に真剣に物件を考えた際、慌てて仮審査を通しました。まずは行動を起こすことが重要です。
下記の「モゲチェック」は、有名で評判の良いサービスです。
私自身もここで比較しました。
メガバンクや地銀以外の金融機関が多く含まれており、「信用して良いのかな?」と感じるかもしれませんが、問題ありません。

少しの頑張りで納得して進めることが重要です。
結果として、リノベーション会社の提携ローンが安ければ、スムーズに進められ、納得感も高まります。
しかし、最も大事なことは、手数料を含めて、最も安い選択肢を選ぶことです。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。